ベートーベン と 「現代のベートーベン」佐村河内守氏
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン - Wikipedia
>聴覚障害について
完全攻略!ベートーベン : ベートーベンの苦悩
>ベートーベンと難聴
>ベートーベンはどうやって難聴を克服したのか
>音を「聴く」から「感じ取る」へ
>ベートーベンは、特製のピアノを発注し難聴の克服に
>乗り出しています。ピアノは、張り詰めた弦をハンマーで叩いて
>音を出す弦楽器の一種なので、弦を叩いた振動が伝わってくる
>ようにすれば難聴のベートーベンでも音の強弱を把握することが
>できます。一説によれば口にくわえたタクトをピアノに接触させて、
>歯を通して振動を感じたとも言われています。
>ベートーベンは今で言う骨伝導を利用して音を感じていたのです。
>ベートーベンは、感じ取った音と耳が聴こえていた時期の
>音の記憶と音楽知識で作曲を続けたのです。作曲以外のときは、
>筆談と聴診器のような補聴器の原型で会話を行っていたようです。
補聴器:慶友銀座クリニック
>歴史上一番性能の良い補聴器は、多分ベートーベンが使った
>補聴器ではないでしょうか。ベートーベンは耳が不自由だった
>にもかかわらず、素晴らしい曲をつくりつづけました。
>彼の補聴器は、ラッパ型でピアノの上に置くようなとてつもなく
>大きな物だったそうです。当然電気もない時代の補聴器ですが、
>筒の中に音をいれて音を大きくするという単純な構造ですが、
(中略)
>ベートーベンの補聴器は、筒を大きく長くしたもので、
>電気的な音よりも自然の法則で大きくしたのですから当然
>たいへんすばらしい音質で、これ以上の音質の補聴器は
>まだ現代にはありません。はじめは、「こんな大きな補聴器は」
>と思い、苦笑したこともありましたが、理論的にもすばらしい音が
>でるのであれば、耳が不自由であっても、あきらめることなく、
>すばらしい曲を書き上げることができるのだと納得した次第です。
補聴器愛用会 : 補聴器の歴史
>ラッパ型補聴器
>1808
>ラッパ型補聴器で良く知られているのは作曲家ベートーベンが
>使用した物です。上段、左側からラッパのような形をした三つは
>大作曲家が実際に用いたものです。20歳代後半に聴力の
>異常を感じ、晩年には殆ど聞えない状態となっていましたが、
>創作意欲は衰えず、多くの名曲は聞こえが不自由になってから
>作曲されています。
>本人は補聴器はそんなに役立つものとは考えていなかった
>ようですが、外出時には写真の上、一番左にある小さなものを
>ポケットに入れ持ち歩いていたとのことです。
>左から三番目のものはメトロノームの発明者で知られる
>ヨハン・メルツェルがベートーベンの為に作ったものです。
>ベートーベンはメルツェルの為にメトロノームのチクタクという音を
>真似たカノンを作曲し、感謝の念を表しています。
価格.com - 『スピーカーの音量と難聴について』
スピーカーのクチコミ掲示板
>梅こぶ茶の友さん
>また余談ですが、以前ベートーヴェンハウスに行った際に
>改造ピアノを見ました。これは、ピアノの鍵盤からダイレクトに
>振動板が出ていて、口でそれをくわえて骨導で聴いていたと
>考えられる品物でした。ベートーヴェンの執念というか、
>その姿を思い浮かべるだけで胸が熱くなりました。
「現代のベートーベン」佐村河内守氏
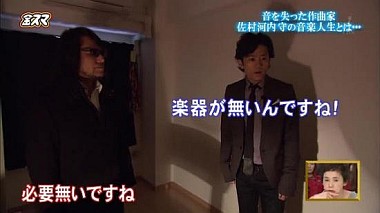
稲垣メンバー「楽器が無いんですね!」
佐村河内「必要無いですね」キリッ

(画像:pic.twitter.com/pmKldlMnlt) |
|